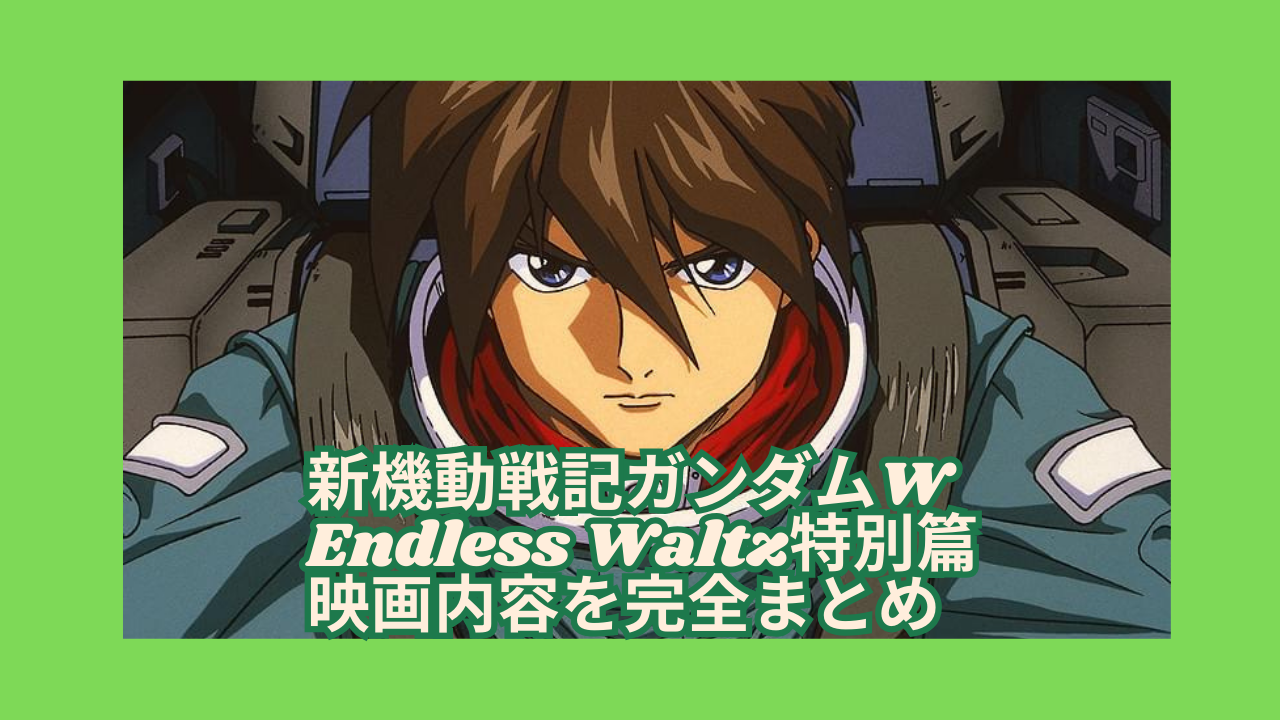作品概要(まずは事実整理)
2025年6月6日公開。監督は『悪人』『怒り』の李相日、主演は吉沢亮、共演に横浜流星・渡辺謙・高畑充希・寺島しのぶほか。原作は吉田修一『国宝』で、任侠の家に生まれた青年が歌舞伎の世界で女方として“国宝”へ昇り詰める半生を描く。原作者は本作を「100年に1本の壮大な芸道映画」と評している。
裏話①:主演陣は“1年半”の歌舞伎稽古——すり足だけで2カ月
吉沢亮は撮影前から約1年半、すり足だけで2カ月続けるなど苛烈な稽古を実施。女方の所作を体に刻むための土台作りがまず徹底され、そこから演目ごとの動きへ発展させたという。
裏話②:歌舞伎指導は中村鴈治郎——“型”の擦り込み
歌舞伎指導は上方歌舞伎の重鎮・中村鴈治郎が担当し、自身も劇中に出演。女方の手先・目線・重心といった“型”の精度を俳優陣へ「擦り込み」、映画ならではの近い距離の画でも破綻しない所作を作り上げた。
裏話③:振付・所作の専門チーム×李監督の“型の先の感情”
所作や振付の訓練は専門家・谷口裕和が担当。李監督は「型ができあがった先で、キャラクターの生身の感情が突き破って出てこそ『国宝』の歌舞伎シーンになる」と語る。つまり“型→感情”の二段階設計で演出が組まれている。
裏話④:本物の場に寄り添うロケ——国立劇場や花街の質感
ロケ地には、国立劇場、国立文楽劇場、京都の先斗町歌舞練場・上七軒歌舞練場、東寺、出石永楽館など“芸の現場”そのものが多数。花街の空気や劇場の光の粒度まで画に取り込むことで、作り物感のない時代の手触りを確保している。
裏話⑤:撮影部・美術部は国際級——“目で語る”画作り
撮影は『アデル、ブルーは熱い色』のソフィアン・エル・ファニ、美術は『キル・ビル』の種田陽平。舞台芸術の“距離”を映画的に縮めつつ、汗や息遣い、指先の震えまでを拾うための照明・美術設計が敷かれた。
裏話⑥:完成披露の場も“国宝級”——京都・東寺でのジャパンプレミア
公開直前のイベントは京都・東寺で実施。五重塔に囲まれた特別な場で、主要キャストと李監督が作品の覚悟を語った。作品の精神性と会場選定がシンクロした象徴的なプロモーションだ。
裏話⑦:興行と海外展開——“芸道映画”が大ヒットへ
公開から約2カ月で興収は100億円を突破。8月17日時点で105億円、8月22日時点で110億円超に到達。さらに9月3日には北米配給(GKIDS)&2026年初頭劇場公開が発表され、国内外での評価が加速している。
制作体制の強み(E-E-A-T視点)
- 一次情報の厚み:原作者・吉田修一は実際に3年間、歌舞伎の黒衣として楽屋に出入りした体験を小説へ反映。映画公式でもその経緯が明示され、取材蓄積に裏打ちされたディテールが土台にある。
- 専門家監修:歌舞伎指導=中村鴈治郎、振付=谷口裕和の体制で“型”を保証。俳優の長期稽古により、カメラの寄りにも耐える所作を担保。
- 国際標準の技術陣:撮影・美術など、国際映画祭常連のスタッフが参加。舞台芸術の質感を映画言語で再構成している。
まとめ:『国宝』は“型”と“感情”をつなぐ映画的挑戦
本作の裏側で見えてくるのは、①長期稽古で“型”を身体化、②指導・振付・演出が“型の先の感情”を引き出す、③実在の場の空気を画に封じ込める——という三点の徹底だ。結果として、歌舞伎の美と人間の生き様がスクリーンで有機的に融合し、国内の大ヒットと北米公開決定へとつながった。公開後も舞台・映画の双方に波及効果を生む“芸道映画”として、今後の賞レースや海外の受容にも注目したい。
主要出典(検証用)
公式サイト/スタッフ・キャスト・制作趣旨、原作者コメント。
Eiga.com/作品データ・公開日。
Walkerplus/歌舞伎指導=中村鴈治郎。
シネマトゥデイ/振付・谷口裕和、演出意図。
地ムービー/ロケ地一覧(国立劇場・花街ほか)。
Walkerplus・Cinemacafe/興収推移(105億→110億超)。
※本記事は9月4日(日本時間)の公表情報に基づく。今後の数字や公開計画は更新される可能性がある。